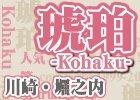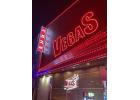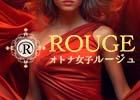知って得する!遊郭ガイド
遊郭の史跡ガイドでは、各県に存在する遊郭についてわかりやすく解説しています。ソープランドの起源である遊郭、ソープランドで遊ぶなら知っておいて損はないでしょう。
1分で横浜遊廓!
外交目的で造られた遊郭の悲しい最後
横浜に昔あった港崎遊郭は外交目的で造られた。その中で最大の遊女屋は岩亀楼という。慶応2年、開業7年に焼失して、永真遊郭に移転した。 永真遊郭は現在の永楽町と真金町にあたる。永楽町には、明治21年に開かれた永真花街と呼ばれた遊郭があった。周囲は壁に囲まれていて出入口は 永楽町側の大門と大島神社側の裏口だけであった。大正12年の大火で遊郭が廃止され、カフェー街として復興した。カフェーとは、明治終わりから 昭和の中頃まで流行った、女給のサービスを売りにした風俗営業店。カフェといっても単に飲食物を提供する純喫茶とは異なり、現在で言う クラブ・ラウンジのような意味合いがた。
A. 港崎遊郭
横浜遊郭の入り口、港崎遊郭
港崎遊郭は幕末の日米通商条約により横浜が開港された際に、
当時駐留していた日本人と外国人の間に争いが発生するのを防ぐため、
幕府主導で現在の横浜スタジアムがある場所に建設された。
規模としては15軒の遊女屋に330人の遊女が在籍していた。
まだ開国されたばかりであったこともあり、この遊郭内では、
外国人用の遊郭と日本人用の遊郭に分けられていた。
そして当時外国人は野蛮な人種とみなされていたことから、
当時の日本人は外国人と関係を持った遊女は抱きたくなかったことが
うかがえる。
また、外国人に抱かれた遊女は家畜以下とみなされていた。
慶応2年、開業7年で焼失し、永真遊郭へ移転した。
永真遊郭跡地である真金町は昔、遊女屋が建ち並んでいたせいか、現在でも風俗店が多く建ち並んでいる。
 1
1
 2
2
 3
3
 4
4
1:明治期
2:現在
3:明治期
4:浮世絵
B. 岩亀楼の灯篭
失われた岩亀楼、最後の灯篭
この灯篭は、幕末の開国の際に外交目的で建設された港崎遊郭の中で 最大の遊女屋であった岩亀楼のものである。慶応2年に起きた大火災で その岩亀楼は焼失し、この灯篭だけが残った。現在でも横浜公園内に 存在している。
横浜ドームの近くにあるから、試合を観たついでに立ち寄ってみてもいいだろう。
 1
1
 2
2
 3
3
1:灯篭
2:横浜スタジアム
3:横浜公園
C. 岩亀稲荷
岩亀横丁の歴史、岩亀稲荷神社
岩亀稲荷神社とは、岩亀楼という遊郭の遊女が、静養のため利用した 寮がここにあったことから岩亀と呼び、岩亀に祀ってある稲荷様 ということから『岩亀稲荷神社』と呼ばれている。この神社は 毎年5月25日に例祭が行われている。
岩亀稲荷神社のある岩亀横丁には、古い酒屋や食堂が建ち並ぶ。食事をするついでにでも寄ってみるといいだろう。
 1
1
 2
2
 3
3
1:祠
2:神社入口
3:岩亀横丁
D. 金刀比羅大鷲神社
岩亀楼住人の努力の結晶、金刀比羅大鷲神社
この神社は岩亀楼主人、つまり遊郭の経営者によって建立された 色鮮やかな神社。場所はかつて遊郭であった真金町にある。 毎年11月の酉の日に酉の市が行われ、露店と、熊手を求める客で 賑わう。
玉垣の寄進者を見ると、なんと「桂歌丸」の文字が。そう、あの落語家 桂歌丸氏である。桂歌丸氏は生まれも育ちも真金町。祖母が経営する 富士楼という置屋で育ったという。ここを訪れたらぜひ探してみてほしい。
 1
1
 2
2
 3
3
1:玉垣の寄進者石
2:酉の市
3:金刀比羅大鷲神社